第十九回南のシナリオ大賞最終審査会ドキュメント
- 11月9日
- 読了時間: 36分
更新日:11月12日
第十九回南のシナリオ大賞最終審査会ドキュメントををお届するにあたり、今回は改めて二次審査通過作品のご紹介と審査風景の様子を画像でご紹介致します。
二次審査通過作品を改めてご紹介します。
はるかな HOME TOWN
波の音、夏の星座
博多発新宿行き
和火屋(わびや)~願いの線香花火~
きみの一歩が
うたかたな僕ら
水たまりの夜に
カレイの煮つけはパンに合う?
では、最終審査に残った8作品について意見を出していきましょう。『はるかなHOME TOWN』からお願いします。
【はるかなHOME TOWN】
皆田:全体的に、いろいろと疑問が多かったです。最初の悟のモノローグ「いったい俺は何のため、誰のために働いてきたんだろう」がこの物語の問いであって、大事なところだと思うんですが、最終的に故郷の平戸に帰ってきてその答えは出たのか? これから見つけていくのかもしれないけどそんな気配は感じられない。また、その後のモノローグ「窓から海が見えるからってここに家を建てたのに」。れが今住んでいる東京(?)の家なのか、すぐにはわからなくて混乱しました。その後の「もう逃げられない」も誰から、何から逃げているのか? わからないです。れから「秋の風の音」ってどんな音でしょう?
盛多:以前「ススキが風に揺れる音」というのは作ったことがありますが。
皆田:奥さんから離婚され、娘とも疎遠になって故郷に帰ってくる……うーん、よくある話で、ドキドキ、ワクワク感は感じられなかったですね。
松尾:都会と地方、過去と現在、親と子、などが交差する3幕構成的な展開を上手に混ぜてある作品だと思います。私も、悟は平戸の実家を想って海の見える一戸建てを建てたのかなと思ったんですが、確かにわかりにくいですね。悟が仕事人間になった理由、悟の父親がパチンコで借金作って家族みんなが大変な目に遭ったからということですが、もっと掘り下げて描いた方が良かったのでは。父親が築けなかった安定を俺は必死に働いて作ろうとしたんだ、みたいな。あとはタイトルの引きが弱いかなと思って。例えば、最後のセリフ「ただいま」を持ってくるとか「波の音の向こうから」はどうでしょう。
町田:読みやすいし、作者は書き慣れている方でしょうね。飛行機の音、連絡船の音などを効果的に使っていて、ラジオドラマをわかっていると思います。疑問に思ったのは、なぜ奥さんは娘が27歳にもなってから離婚を切り出したのか。大学卒業や就職を機にではなく。また、美空は子どものとき祖父の葬式に行ったきりで、その後おばあちゃんに会っていない。悟は仕事ばかりだし、美空の寂しさを奥さんは一番よくわかっていたはずなのに、なぜ一度でもおばあちゃんに会いに行かなかったのか。最初からこの夫婦は冷えていたのか、奥さんの方も何か問題があったのか。それに、果たして美空は子どもの頃一度会ったきりのおばあちゃんの面倒を見ようと言い出すだろうか?もう仕事が嫌になっていたとしても、と色んな疑問が湧いてしまいました。綺麗にまとまってはいるけど、人間関係や心模様をもう少し丁寧に描いてほしかったです。最後、「ただいま」で終わるのはいいと思いました。
日高:テンポがいいし、構成もしっかりしている。家族愛や故郷の大切さを描いていていい話だと思いました。ただ、仕事ばかりで家庭を顧みない父親、それに反発するも心根は優しい娘、ユーモアがあって皆を温かく見守るおばあちゃん、という登場人物は若干ステレオタイプで既視感がありました。話の流れも予想通りにいく感じ。作家の個性やこだわりがあまり感じられなかったのが残念でした。モノローグの使い方ですが、主人公悟のモノローグはいいとして、途中で美空のモノローグもある。一つの作品のなかで2人がモノローグを使うのはどうなんでしょう?
盛多:よく出来ているドラマです。ですが、またこういう話か、という感じ。それに気になることがいろいろあって。主人公は仕事で忙しいというけれど、じゃあ何の仕事をしているのか、おかあさんは何の病気で倒れたのか。そういう細かなことが抜け落ちていると、どんどんドラマが薄っぺらに感じられてしまう。美空が祖母に会社を辞めたことを告げるシーンでも「やることが親子、そっくりたい」というセリフ、ここもよくわからないです。モノローグの件ですが、僕は2人も有りかと思ってます。以前FMシアターで聴いた作品は、2人モノローグによって、よりわかりやすくなっていました。ですから1人にこだわらなくてもOKかと。
香月:全体的にいうとわかりやすいです。よく出来ている。引っかかりもなく流れていくし。でもあまりテンポがない。というのは、セリフでどんどん進んでいくのではなく、前を受けて追いゼリフになっているからなんですね。人の動きがあまり活発でなくて、若干かったるい感じがします。冒頭、設定をモノローグで説明しているんだけど、ドラマが進行していく中で明らかにしていく方がいいんじゃないかな。残念なことに、この作品はテーマも構成も若干古臭い感じを受けます。2人モノローグは、自然に感じられるならあってもいいと思いますが、僕も少し唐突な感じを受けましたね。
【波の音、夏の星座】
町田:石垣島を舞台とした16歳の男子高校生と20歳の女性のお話。第15回大賞受賞作品『オルガニストを探しに』に似たところがあって、思い出したんですが。あちらの方が深いお話だったなあと、どうしても比べてしまったところがありました。説明セリフが多いですね。2日間の話なんですが、展開が早く、主人公波音の気持ちがこんなにトトトッと変わっていくことに違和感を覚えました。この女性は、波音が何年後かに東京に出てきても忘れているんじゃないでしょうか。そんな軽い気持ちが見えましたね。「波音」「莉音」2人の名前に「音」が入っているのは綺麗でいいなと思いましたが、それが活かされている訳でもない。ラスト「僕たちの願い事は、これから自分で叶えるんだ」はいいセリフだと思いました。
松尾:セリフ、長いですね。莉音が初めて海で波音に会ったとき、自分の名前を言うんですが、普通言うかな、「私は莉音」って。それが彼女のキャラなのかもしれないけど、ちょっとアニメっぽい。これを書くに当たって、作者にはハッキリと映像が見えているんでしょうね。それを書いていたらセリフがどんどん増えちゃったのでは。おそらく莉音に対してかなり思い入れがあって、もしかしたら自分を投影しているのかなと思いました。テンポが速いのもアニメっぽい。この莉音さんのキャラだとやっぱり彼氏に振られるかなあという感じで、それが彼女の魅力なんでしょうが、東京で波音を待ってはいないでしょうね。
皆田:夏、南の島、女性が旅して男性と出会う。これもよくある話だなと思いました。主人公は高校2年生ですよね。よくわからないセリフが多い。女性が自分の名前を説明するところ、「マリカ」って何ですか?
町田:「茉莉花」、ジャスミンのことみたいですよ。
日高:音だけだとわからないですよね。
皆田:ペルセウス流星群のことを書きたくてこのお話を作ったのかな。高校2年の男の子が将来建築を勉強したいとか、すごいなあって。年上の彼女に対して「莉音は莉音のままで良い」とか、出会って間もない年上の女性にそんなこと言えるんだ、へえーって思ってしまって、僕には響きませんでした。ラスト「僕たちの願い事」ってありますが、波音はわかるとして、莉音の願い事って何ですか? 書かれていませんよね。
日高:若者の青さ、瑞々しさが感じられて、そこは素敵だと思いました。ただ、ツッコミどころ、多かったです。一番気になったのは、莉音のキャラクター。作者は莉音を魅力的に描きたいはずなのに、それが伝わってこない。出会いのシーン、ビール飲みながらのセリフなんですが、これは音としても綺麗じゃないし、ずけずけとモノを言うカンジ悪い女としか思えなかったんですよね……。二人とも出会ってからすぐに長ゼリフで自分のことを打ち明けるんですが、不自然な気がします。最初と最後、波音が莉音のことを「夏の星座のような彼女」と言っていて、しかもタイトルにもなっている。そんなに重要なことなのに、何を意味しているのか? ひと夏の出会いを例えているのか、それともキラキラした美しいものの象徴なのか? わからなかったです。別れ際の莉音の「早く大人になってね」も、なんだか変な気がしました。
盛多:ストーリーが単純すぎて、何の事件性もなく終わってる感じがします。そして、セリフにあまり魅力を感じなかったですね。説明ゼリフで長いんですよ。作者がストーリーを考えて、それをなぞっているセリフ、つまりセリフがストーリーを進めていくためだけのものになっている。最後「これから自分で叶えるんだ」にしても、そうじゃなくて、コイツもっと悩むだろうって思っちゃったんですね。東京行くにしても年上の彼女に会うにしても、躊躇するとか。なのにストレートで来ちゃうので……。
香月:キラキラ感がありますね。そこが僕は好き。この作者独特の世界観があります。ただ、正直言うとちょっと退屈ではありました。面白くするテクニックが足りないんです。作品は作り手のものだけど、読み手聴き手のものでもあるので、もっとチャーミングにしないと。例えば何か事件を起こすとかセリフをイキイキさせるとか。キラキラ感は良いので、テクニックをもう少し勉強すると良くなっていくんじゃないでしょうか。
【博多発新宿行き】
日高:こちらの作者も書き慣れている印象で読みやすかったです。おにぎりをくれた若者が30年前の自分だった? というのは驚きだったし、そう来るか!という感じで。ラストに向けての盛り上がりも上手ですね。気になったのが「やけん」から始まるセリフが冒頭、由美のセリフだけでも2回あって。これは「だから」という意味? なんだか意味が通らない気がしたんですが。気になりませんでしたか?
盛多:親しみのある表現としていいんじゃないですか? 由美は後でわかるけど、真治と元つきあっていたということもあるので。
日高:なるほど。いえ、他の皆さんが気にならなければいいです。それと、真治が若者に自分のことを打ち明けているシーン。母親に「やっぱり真治じゃダメやったか」って言われて嗚咽するところですね。大の大人がいきなり泣くかな? って。ちょっと唐突な感じを受けました。後、主人公の真治は母親からおにぎりをもらわなかった人生を今歩んでいるわけですよね。若者が30年前の自分だとしたら、彼は母親からおにぎりをもらった人生を歩むわけで。タイムラインが2つ出来ちゃうのか? 考えるとよくわからなくなってきます。
町田:私はこれを読んだときに、雪で飛行機も新幹線も止まってるのにバスは走るのかなあと疑問に思ったんですね。でも話の中で30年前の自分が出てきたとき、全部許しました、疑問も何もかも。なぜなら、ああ、これってファンタジーだ、って自分の頭のなかで切り替わったんです。そうして読んだら、私はこれ、とっても大好きな作品でした。私も自分の息子が大学進学で外に出て行ったときにおにぎりを持って追いかけたことがあるんですね。それでウルッと来て、この物語はとても心に残りました。是非ラジオドラマで聴いてみたい作品です。
松尾:町田さんの感想を聞いてウルっと来ます。。
日高:やっぱり母はおにぎりですよね。町田:しかも高菜。九州ならでは。
松尾:シンプルでいい作品ですね。最後、終わり方がちょっと唐突な感じを受けたかな。もうちょっとあるかなと思ったらあれ、もう終わりか、みたいな。
日高:私は戻ってどうすんだ、って思っちゃったけど。
町田:お母さんにありがとう言ってないから。会い直し。
松尾:スケールの大きな話じゃないけど、とても自然に物語が流れていく。セリフも自然だし。「南のシナリオ」にはまってる感じがします。
皆田:この話も良くあるパターンな気がしますが……まあ。これ、聴いてたらわからないんだろうけど、読んでたら「真治」「シンジ」で自分だってことがわかっちゃって。でも話の流れとしては良い。あとはここも良かった、バスの中でシンジと真治の会話が一旦終わるんだけど、シンジが「ああ、ダメや。おじさんの話の続きが気になって集中できん!」で、また2人の会話が続いていくところ。これって、ファンタジーなのか、どうなのかな……? 後は、元カノが兄さんの嫁さんになってるとか、お母さんがせっかく仕事を継いだのに潰しちゃった次男に「やっぱりダメだった」って、そんなにおとしめるかなって。
盛多:そのセリフきついなぁ。
皆田:ここもわかりにくい。「でも兄さんは経営学部やろ?」「やけん法学部であと2年頑張るんやと」弁護士になりたいから後2年行くってことなんだろうけど。また、母親の気持ちを後から兄さんが代弁するじゃないですか。この手法はどうなんだろう。ここは一番大事なところですよね、本当は母親も真治を応援していたってこと。ここは手紙なりで母親の言葉として書いた方がいいんじゃないでしょうか。兄さんが嘘ついてると疑う訳じゃないけど。
盛多:僕はそこのところに関してはいろんな感情が渦巻いてる。現実的にはお兄さんが母親の気持ちを伝えるしかないと思うんだけど、弟の恋人を取ったお兄さんってどうなの? とか。だから母親の気持ちを伝えることで罪滅ぼししてるのかなあ、なんてことも思っちゃう。細かいけどどうしても気になるのは、めかりパーキングエリアから門司港まで9.5キロ、冬の真っ盛りに歩いて2時間かかるんですよ。もう深夜でバスは走ってないのに。
町田:走ってても走ってなくてもこの人は帰ろうと思ったんですよ、お母さんのところに。歩いてどれだけかかろうとも。
盛多:40いくつかの、しかもアニメの会社の部長やってて、現実面もわかってる男が、それを計算しないで降りちゃうのかと思って。
松尾:感傷的になったんじゃないですか?
町田:この人は実家には嫌な思い出しかなくて何十年も寄り付かなかったのが、お母さんの本当の気持ちを知ってからは、もう戻る選択肢しかないんだと思います。
盛多:僕にはちょっと理解できない。それと、高校生のシンジはこの男(真治)が自分の未来だとわかってるんだっけ?
町田:わかってるんじゃないですか? ファンタジーだから。盛多:いや、僕はファンタジーと思ってなくて。わかっているのかどうか、それがはっきりしていないと、これを演出するときに役者に説明できないですよ。
町田:私はこのシンジは現実にはいないんだと思っています。幻というか。
香月:幻想ですよね。車掌がそこは誰もいなかったと言っている。僕は、シンジのセリフには何か異次元のものを思わせるような演出が必要かなと思ってますけど。
盛多:何度も言うけど、やっぱり冬の夜中、めかりから門司港まで歩くのが現実的に変だと思う人もいるわけじゃないですか。それを気持ちだけで押せるかどうか。事実と違うことをやると、何かひっかかってくるんですよ。
香月:僕は作者から騙されたのが快感だったけどね。
盛多:うーん。
香月:ラスト、男の情熱があったらできるんじゃないですか? 何分かかっても。
皆田:博多までタクシー飛ばしてもいいんでしょ?
松尾:私もそうするのかと思った。
香月:騙すにもボーダーラインが必要で。
盛多:そこの線引きが難しい。
香月:これは完全に騙してるから。伏線が必要だったかもしれないですね。
皆田:でもさっきも言った通り、名前が「シンジ」「真治」ってところで気づく人もいるかもしれないですよ。
町田:シンジが「美大を受ける」、真治も「美大を受けた」、この辺でわかる人もいるかもしれません。
日高:ジワジワわかるようになっている感じはしました。
盛多:とにかくこれは僕にはファンタジーじゃなくて。リアリティーのあるドラマとしか思えないんです。
町田:ファンタジーだと思いますが。
盛多:いや、お兄さんが自分の彼女を取ったとか、これ完全にリアリティーじゃないですか。人間の気持ちを優先して、きちんとリアリティーのあるドラマに作った方が迫ってくるものがあると思うんですよ。
日高:つまり盛多さんの主張は、これはファンタジーじゃない、だから最後の終わり方もファンタジーでなく、リアリティーを追求すべきというわけですね。
盛多:そうです。そうでないと、最後落とし込めない。母親の気持ちも伝わってこないし、おにぎりも活きてこない。
香月:僕はこれ、ファンタジーかそうでないか、よくわからなくなってきた。『終わりに見た街』って山田太一のドラマがあったじゃないですか。あれ、ファンタジーですか?
盛多:いや、リアリティーのあるドラマという風に感じました。
香月:僕もそうです。これもあれと同じような感じですね。ファンタジーなら最初からそういう立ち位置がないといけないんだけど。シンジだけがファンタジーで。でも、全体的なことを言うと、僕はこのドラマ大好きです。面白い、流れも自然だし。読ませますよね。多少博多弁の修正が必要ですが。
僕が一番大事と思うのは、雪でバスが走るか? ということ。解決策としたら、例えばシステム障害で飛行機や新幹線がダメになる、だったらいいかもしれません。
日高:バスが走ること自体が、そこからファンタジーになってるみたいですよ。
真治がバスターミナルに行ったら、ちょうど発車するところだったし。
香月:ここが勝負の分かれ目という感じがします。それと、終わり方があっさりしているという意見も出ましたが、僕は好きです。ここも意見の分かれるところですね。
町田:これだけいろんな意見が出るのは、良い作品だということですね。
香月:真治がヒーローじゃなくて駄目男だってところがいいですね
【和火屋(わびや)~願いの線香花火~】
皆田:タイトルが途中で入ってるけど。盛多:タイトルは通常、冒頭ナレーションで入ります。皆田:赤目のセリフ、「本当さ、火花は一瞬で消える。けど、誰かが覚えていてくれたら、ずっとその日は心の中で、燃え続けられるだろ」これがポイントだと思うんですよ。悟は毎日花火を買って、願いが叶う花火を引き当てる、そうしたらおかあさんが早く帰ってきて、長崎の花火大会にも行く、お父さんが亡くなったときのことを聞く。10歳の悟がそれまでお父さんの死因を知らなかったのかな? という疑問はありますね。この作品、なかなかラジオじゃ難しいのかなあ……花火の音とか。最後おかあさんは「ママこれから頑張るけん」って言いますが、これ以上頑張るの? もう今、働いて働いているじゃないですか。「いつの間にか悟との時間を諦めとった」も、そんなことあるかな?って感じで。疑問に思うセリフが多かったですね。
松尾:この作者もアニメが好きな方のような気がします。アニメっぽく頭に映像が浮かんでいて、それを書かれたのでは。キャラクターですが、私も悟くんが10歳でお父さんの死因知らなかったんだ、と疑問に思ったのと、お母さんが悟くんを探しに来て急にキレたように怒るのが怖くて。ちょっと違和感がありました。
日高:そこ、私も同じです。松尾:作者は赤目さんを一番書きたかったんだろうなと思って。赤目さん推し。口調も独特ですよね。皆田:あれ? NHKドラマの。
盛多:『不思議な駄菓子屋銭天堂』ね。あれも猫なんですよ。映画化もされました。
町田:不思議でノスタルジックなお話でしたね。以前創作ラジオドラマ大賞で、これに似たような話があって……お祭りの日に猫(?)か何かについていったら不思議な呑み屋があって、そんなような話でした。それも、亡くなったお父さんと関係していたんです。あとは私も母親が怒るシーンが気になりました。まず怒るのが普通なのに、プリン買ってきたと言ってから怒るのが変な気がします。母親が父親の死を語るシーン、最後の方でバタバタッと説明するので……もう最後だからここで入れとかないと、って書いたような感じを受けました。主人公の悟くんってとてもいい子で。だから、このおかあさんはずっと働いていて大変だけど愛情を持って育ててきたことがわかる。暖かい優しい物話だと思いました。ラジオじゃなくて映像で見たいかな。
日高:独特で不思議な世界観がありますね。趣深い、風情、雰囲気があるというのかな。私は好きですね。悟が猫に誘われて神社に行って「和火屋」があるところ、ここはもっと聴く人の想像が膨らむような……素敵なシーンなので、もっと工夫を凝らして魅力的に描いて欲しいなと思いました。いろんな花火があって最後に買ったのが、願いが叶う花火、ここも素敵でしたね。舞台は長崎の近くなんですかね。おかあさんも悟も若いのにちょっと方言が強い感じがしましたが。松尾:すごく田舎ならそんな感じかもしれません。
盛多:どうしても『不思議駄菓子屋銭天堂』が頭から離れないんです。『銭天堂』でも猫が案内して、花火を買った2人が仲良くなるという話があるんですよ。そのせいでどうも深読みできなかった、というのがありました。
香月:出だしがちょっとだるい感じですね。あまりチャーミングでない。後、このお話は猫が何度も出てきますが、映像は良いけれどラジオドラマの場合、猫は使いにくいですね。ちょっと難しいと思います。
【きみの一歩が】
皆田:最初、設定が面白い! と思ったんですよ。これはスニーカーくんが歩くんと別れる、歩くんは転校してきたばっかりで友だちがいない、みんな心配してる、でも歩くんは頑張って友だち作ってるから、スニーカーくんもサンダルさんに声を掛ける、そんな話ですよね。でも、最初ワクワクしたのが途中から、うーん……。というのは、スニーカーくんやバッシュ、ローファー、革靴、皆で歩くんを応援するのかと思ったんですよ。そうじゃないので、ちょっとガッカリしてしまって。捨てられるはずだったスニーカーくんが歩くんのために一肌脱ぐのかなあ、なんて思ったりもしたんですが。
松尾:これは絵本だと思いました。絵本にした方がこのシナリオは活きるような気がします。今回最終審査に残ったのはファンタジー要素があるものが多かったですね。この作品はちょっと聴き手を選ぶのかなという感じ。お子さんをお持ちの方とか読み聞かせをする人、子どもさんとか。ジャンルの好みもあると思うし。歩くんがバッシュを履いて、さあ今日も頑張るぞ、みたいなセリフがラストの方であるといいかなと思いました。タイトルは、もっと可愛い方がいいんじゃないでしょうか。「きみの一歩が」だとスポ―ツ少年っぽい、サッカーとか走る系な感じがします。
町田:シナリオが綺麗で読みやすかったです。書き慣れていらっしゃるんでしょうね。登場人物が靴というのが奇想天外で面白い。靴を擬人化して命を吹き込んだことに拍手を送りたいです。それぞれの靴のキャラが立っているのもいいですね。これが絵本になったら、買ってでも子どもに読んで聞かせたいくらいです。スニーカーはサンダルと同じところ、ベランダに置かれるんだけど雨のときはビショビショに濡れてしまうんじゃないかな。これを読んだら、靴に感情がある気がして捨てにくくなりました。とても可愛くて好きだけれど、「南のシナリオ大賞」というよりは絵本だな、という感想です。
日高:登場人物が靴って面白いですよね。私もこれは絵本だなと思いましたが、とても好きです。初っ端からテンポが良くてどんどん進んでいくし、それぞれのキャラが立っている、わかりやすい。スニーカーくんのセリフが健気で泣けるんですよね、いじらしいし可愛い。その素直さが良いなと思いました。深刻でないこんな軽いタッチの作品もいい。「友だちと仲良くしよう」を説教臭くなく描いている。2階のベランダに置く履物って、パッと履けないといけないからサンダルはわかる、でもスニーカーは置かないだろう、というツッコミはありましたが。
盛多:いい話ですよ。でも、皆田さんの感じたのに似ていて。結構中途半端だなと思ったんですね。作者がどこを狙って書いているのか、よくわからない。全体の流れとして、絵本のようにファンタジーで行くのか、それとも子どもたちのいじめの話に持ってくるのか、それを一緒くたにしているから。
香月:僕はとても面白かったですね。文章が上手い。かなり書き慣れている人でしょう。たださっきから言われているように、靴の話が何だ、という感じ。ちょっと中途半端なんですね。靴の話というから、去年FMシアターであった『うつくしい靴』を思い出したんです。これが素晴らしい作品だったので、期待して読んだんですが、ちょっと残念でした。「南のシナリオ大賞」としてどうかなあ? とも思いました。
皆田:もう少し、歩くんが頑張って変わっていく姿を描いた方が良かったんじゃないかな。スニーカーくんからバッシュくんに引き継ぐときに、歩くんが学校で「遊ぼう」って話し掛けても無視されたことを話すんだけど、バッシュくんが「いや、今日は学校で一人友だちができた」とか、そういう歩くんの成長を伝えてくれたら良かった。そうしたらスニーカーくんも一緒に成長していけたんじゃないか。その方が、話が明確になると思います。
【うたかたな僕ら】
町田: 面白い作品だと思いました。信夫がルミという女性になりきって樋口と話をしているんですけど、途中、女性の声の変換が失敗して男性の声に戻るシーンは、ラジオドラマにした時に面白いんじゃないかと思いました。鴨長明の『方丈記』が出てくるので、どんな話だったかと読み返してみました。800年以上前に書かれたものなのに、人生観など現代人にも繋がるものがあって感心しました。生徒達が信夫につけたあだ名『催眠術師』の言葉のセンスも面白かったです。ギャグみたいな感じで進んでいくドラマですけど、中身は深いものがあると思いました。私は好きな作品でした。
松尾:ルミさんとはPCで繋がっているのかな? 声だけなのかな?
盛多:(顔は)AIで加工できるからですね。
松尾:ルミは男性だとバレた後、樋口の携帯に電話しますよね。ということは、携帯番号を知っていることになりますよね?
盛多:ま、そうでしょうね。
松尾:だったらラジオドラマを作る時には、PCの時の音(声)と携帯の時の音(声)を変えないといけないですよね。文字で見るとわかるけど、音で聴くのであれば、違いを作らないと聴いている人はわからないです。
(内容には)知的な部分もあるし、『方丈記』を検索する人も出てくるかもしれないし、あと、女子高生の反応が今風でよかったですね。「古文漢文とか知らんめーも」という桜さんのツッコミが面白かったです。登場人物がそれぞれの役割を果たしていて、シンプルでわかりやすかったです。
皆田:鴨長明の『方丈記』は知っていますけど、中身をよく知らないので、内容がよくわからなかったですね。最後、授業で方丈記を樋口が生徒に読ませようとするが「えー、しゃらくさい!」と、突然、俺の解釈で訳すと言いだし「好きな事をして生きるのが、一番楽しい」と……方丈記の内容を知らない人に、これを聴かせてもピンとこないですよね。授業中に生徒達が寝てしまうことから催眠術師というあだ名をつけられた教師の樋口と引きこもりの中年男性や生徒達。色んな要素は入ってきてるんですが、誰の物語で、樋口さんがどう成長したのかが全然わからないです。『方丈記』の内容がちょっとでも紹介されていれば「ああ、そうなんだな」と思うかもしれませんが、僕にはちょっと理解できませんでした。
日髙:古文を題材にしているものがあまりないのと、信夫がルミとなって音声を変えているところもラジオ向きだし、信夫が引きこもりになっているところは時代性を捉えていて、そこは評価するべきところだと思いました。でも、私も皆田さんと同じような感想で、ラストがですね、あらすじを読むと、「樋口は学ぶことの大切さを噛みしめ、斬新な口語尺を語り、現代の子供達へ古文の魅力を伝える」となっているんですが、そこが全然描かれていないんですよね。「よし!今日は俺の解釈で訳すぞ。方丈記は全体的にはこんな感じだ」と……こんな感じって何? って思いました。やはり方丈記を知らない人が音声で聴いたとしても、ピンとこないと思います。大事なラストなのに感動できないので残念に思いました。主人公の勉は、根っからの古文オタクで、それが職業になってるんですよね? 生徒達に理解されないとはいえ、自分の好きなことが職業になるって恵まれてますよね。そういう点もこの物語にグッと入り込めなかったとこでもありました。
盛多:基本的には、鴨長明の『方丈記』を知らない人にとっては、意味を持たないドラマだと思いますね。もっと言うと、それを説明するのは滅茶苦茶難しい。一過性の15分のラジオドラマを聴いた後に、方丈記に結ぶ人って、まず皆無だと思うんですよね。それを前提に考えると、これを持ち出してきているのは無理があるかなと。いつだったか、「古文、漢文は要らない!」という高校生のアンケート結果が出たというのを記憶してるんですが、そのことに集約して、問題があるんですよ!と訴えてドラマにしていくと、メッセージ性が出て伝わってくるんですが……。大前提として、鴨長明の『方丈記』を知っていないと(ラジオドラマにするには)難しいかなと思いますね。
香月:僕らは高校生の時に方丈記は教え込まれたんですよ。「ゆく川の流れは……」の文章は死ぬまで覚えてるくらいに。だから、すんなりと入れました。ただし、方丈記を知らない人が聴いても、全然わからないでしょう。そこは問題だと思います。このドラマは、頭で書かれているドラマなんですよね。ドラマというのは肉感ですからね。そこがないよね。途中で引きこもりの男が出てくるでしょ?あそこがね、ストレート過ぎるんですよ。あそこは引きこもりの男と教師で、ドラマを作らなきゃいけない。ただ、カミングアウトしているだけなんで、全然盛り上がらない。ま、でも、方丈記を習った者としては、読みどころはあったですね。あと、『刀伊の入寇』とか『女真族』という言葉が出てくるじゃないですか?これは、わからない人が聴いても、全然わからないでしょうね。女真族は読み方が二通りあるけど、どっちで読むのかもわからない。振り仮名もないしね。個人的には面白い作品ではあったけど、一般的にはわからないでしょうね。
【水たまりの夜に】
日髙:水たまりと月が心を持ってセリフを喋るという設定が斬新で意外性があって面白いと思いました。水たまりが主人公なんですが「ああ、ごめんなさい。またできてしまいました……」という最初のセリフが、自己肯定感の低い男性みたいな感じで、共感する人もいるんじゃないかと思いました。そういう点では冒頭から心を掴まれました。淡々と進んでいく優しい物語で、全体的な世界観は好きだなと思いました。月が優しくて、看護師の咲子さんを気にかけていて温かい物語だと思います。気になるところとしては、月と水たまりの会話が淡々と続いていくので、退屈するかもしれない……原稿用紙でいうと、8枚から9枚、月と水たまりの会話なので、ラジオドラマとしては盛り上がりに欠けるかなと思いました。ラスト、水たまりに月が映って、咲子さんが「綺麗」と言って癒されるシーン。お互いがお互いの存在を引き立てて素敵なシーンだと思いますが、映像的なので、ラストの4、5行で、ラジオドラマでわからせることができるかな? ちょっと難しいのかなと思いました。
皆田:絵本みたいだなと思いましたが、全体的には好印象です。水たまりは、歩行の邪魔になる嫌われ者で、月は人々に愛されている象徴じゃないですか? 僕は、この二人が恋をするというような話の方がよかったんじゃないかなと思いましたね。月は晴れていないと見えないし、水たまりは雨が降らないと存在しないじゃないですか? 雨が降ると会えない。晴れだと蒸発して会えない。お互いが惹かれ合うというような淡い恋心を持つというふうに持っていくと、最後がいいのかな? と、ちょっと思いましたね。
松尾:物語としては美しいです。モチーフも面白いと思います。大きな展開はなくて水たまりと月の会話と咲子さんの存在がアクセントで入ってくる感じなんですけど、これを演じる役者さんの力で、作品(ラジオドラマ)にはなるかなと思いました。水たまり役の方がもの凄く個性的でクセのある声で、月の方は美しい声で、咲子さんは今風の芯のある女性の声で…。耳で聴いて、明らかに声の違う役者さんで演じると、凄く面白くなるのかなと思って、読みました。水たまり役の人に全てがかかるかと思いましたが…。私自身には音で聴こえる脚本でした。ストーリー的には、何か引っかかりがあれば、ドラマティックになるのかなと思いました。
町田:水たまりを主人公にするというアイデアが面白いですね。月を主人公にという話はわりとありますが。しかも、この水たまり、超マイナス思考で、たぶん、現代の陰キャな若者を擬人化しているんだろうなと感じました。反対に月は大人で、客観的に世界を見つめる目を持っていて、よくこの二つのキャラクター対比させたなと感心しました。ラスト、水たまりに月が映っているシーンは、美しくて音よりも目で見たいと思いました。確かに展開はあまりない物語ですが、セリフがいいし、筋もいい。セリフだけでここまで話を持っていけています。最後の水たまりに月が映っている美しいシーン。たぶん、作家さんは、最初にこのシーンを考えたと思います。そこからこのラストに持っていく話の展開が上手いですね。絵本にしたら上質な絵本になりそうな作品だと思いました。
盛多:最後の水たまりに月が映っているシーンが、作家の発想のスタートでしょうね。この結に持っていく為に、色々な物語を積み重ねていっていると…で、15分の尺で考えた時に、起承転結が要るの? と思っちゃいましたね。15分だと雰囲気で作れるんじゃないかということを考えると、これ、セリフが凄く気持ちいいんですよね。ラストは映像的ではあるけど、音声的でもあるかなという気がしています。香月さんはいかがですか?
香月:詩情は非常に好きでしたね。ポエムを見ているようで……。ただ、作品の世界が小さいという感じはしますね。真ん中くらいから、少しダレてくるんですよ。ずっとダラダラ読まされている感じがしますね。詩情はあるけども、今一歩という感じですね。
松尾:シチュエーションがずっとコンビニの前ですもんね。
盛多:それはしょうがないです。
香月:以前、南のシナリオ大賞を取った、いとう菜のはさんの作品に、盃の中に月を浮かべてグイッと飲むというシーンがあって、それを思い出しましたね。
水の上に月を浮かべるというのは、イメージとしてはよくわかりますね。
【カレイの煮つけはパンに合う?】
皆田:僕はですね、主人公が成長していく姿が見たいというのがあるんですよね。変わっていく姿でもいいんですが……そういう目線で見ると、熟年夫婦は普通なんですよね。65まで働いて、その後はゆっくり過ごそうねと言ってて。旦那さんの方は、朝早くから働いて昼に帰ってくるでしょう? 奥さんは遅番で働いて……夫婦で失敗談もありながらだけど、あまり問題もないわけですよね。熟年夫婦と同じ職場で働く、それぞれの若い男女の方にどういう成長があるかなと思って読んだりしたんですがあまり(変化がない)……カレイの煮つけでパンを食べてみようかなという気にはなりましたがね(笑)。ま、僕が気づかないだけで、もっと深い話なのかもしれませんが、物語の起伏もそんなにないし、共感するところがあまり(なかった)……還暦過ぎての夫婦というのは、そういう感じかなという雰囲気には共感できましたけどね。ラジオドラマにするには……という感じがしました。
松尾:タイトル見て「わ、どういうこと⁉」と思いました。私はエッジが効いた作品が好きなので、これは来たかな? と思って読みました。熟年夫婦の人生ドラマというか、夫と妻のそれぞれの言い分や、若い人達がなぜ結婚しないのかというリアルな世界がそのまま物語になっているなと思いました。最後、救いなのが、お互いが庇い合いながら(日常に)戻るというところが、ホッとしたかなと。とにかくタイトルが面白いですね。この作者は、音で物語を作っている方だなと思いました。SEもきっちり書かれているし、かなり書きなれている方だと思いました。
町田:私もタイトルを見た時に「どんな作品?」と思いました。こういう他愛ない日常が描かれている作品もよいなと感じました。私は好きでした。熟年夫婦の会話は漫才のようで面白いし、今どきの若者の結婚観も入っていて、なるほどと思いましたね。日本では未婚化や晩婚化が進んでいますけど、このドラマを聴いた人達がどう感じるかな?と……私は一緒に年を経ていく、この熟年夫婦の在り方がとてもいいなと思ったんですけど、感じ方はそれぞれですからね。この作品は結婚というものを問いかけている気がして、ラジオドラマを聴く人に、答えを委ねているのかもしれないと思いました。
日髙:タイトル面白いです。書きなれている感じですね。モノローグで状況を説明するんじゃなくて、若い同僚とのセリフの中で自然とわからせていくのがとても上手です。セリフもテンポよくて上手いですね。私が主人公と同年代だからか、「洗濯物取り込んでない!」「炊飯器のスイッチ入れてない!」とかの無念さがよくわかって、面白いと思いました。大きなメッセージ性があるわけでもないし、物足りなさとか、いい人ばかり出てくるなどの感じはあるかもしれませんが、すんなりといいドラマだなと思いました。旦那さんが奥さんに「お前、値引きシール好きだろ?」「大好き!」っていうセリフが好きでした。作者の意図とは違うかもしれませんが、私的には、自分が相手(配偶者)の文句を言うのはいいんですが、他人に言われると嫌なので「ああ、そうだよね」と、そこが心に響きました。(熟年夫婦に)愛があって可愛げがあるから、温かい気持ちになりました。
盛多:明るい話だなと。エンターテイメントで、若者の結婚観と60過ぎた老年夫婦の話がポンポンポンと出てきて、リズムもいいんですけど、だから何? と思ってしまいました。この老夫婦の在り方と若者の現実面というのはよくわかりましたけど、最終的には「だから、何?」という感想ですね。セリフ的には面白いです。
香月:タイトルは面白かったですね。温かい作品なんですけど、ちょっと日常的過ぎるかなと。ドラマっていうのは、日常の中に非日常が必要なんですよね。それが足りなかったかなと思います。SEの使い方がおかしいですよね。“昼の情報番組の音”なんていうのは、これは作らなきゃいけないんですよ、盛多さんが。著作権があるから(テレビの音を)借りては使えないし。あと、“沢山のリネンを移す音”なんてのは、どうやって作るの? とか。“カートを転がす音”とか“炊飯器を開ける音”なんてのも結構難しいですね。ラジオドラマを書くとしたら、このSEの使い方は難しい。細かなことだけど、「口をきく」のきくが、聞き耳の聞くになっていますね。本当は利用するの利なんですよね。字が間違ってますね。それと、防線じゃなく予防線が正しいですよね。ま、ミスかもしれないけど、ちょっと杜撰な感じがします。一番大事なところですが、箱書きをそのままドラマにしている感じがして、ドラマが在らぬ方向に行くとか、誰かが引っ張るとか、そういう面白い要素がなくて、ポンポンと話が進んでいって……それから急に、奥さんも亭主もお互いの肩を持ったりするでしょ? あれにリアリズムがないなと。頭で書いてるからじゃないかな。「ここではこういうことを言わなければいけない、こういう立場にならなければいけない」みたいな箱書き的な書き方になっているのでちょっと残念でしたね。ま、でも、この温かさというのは褒めたいですね。
盛多:これで、最終選考の8作品が出揃いました。この中から、大賞1本、優秀賞2本の3作品を、それぞれ選んでください。休憩を挟んだ後に受賞作品を選出したいと思います。
- 休 憩 ―
盛多:どんなふうに決めていきましょうか。
日髙:昨年は票数を集めたものの中から選んだと思います。
盛多:それではそうしたいと思いますがいいですか?
-「はい」の声あり ―
盛多:票数どおりでいくと、『博多発新宿行き』『水たまりの夜に』『カレイの煮つけはパンに合う?』の3本に絞られますけど…。
香月:『水たまりの夜に』なんですが、満月の一歩手前を十三夜月と書いてありますが、あれは違うんですよね。十四夜は待宵月(まつよいづき)です。十三日が十三夜月でしょ?十四日は待宵月、十五日が満月、十六日が十六夜月(いざよいづき)です。
盛多:(月の呼び方は)それぞれ色々ありますからね。
香月:(これは)満月の一日前ですよね?
松尾:(シナリオには)満月の一歩手前って書いてますけど、一日前とは言ってないですね。
香月:一日前なら待宵の月なんですよ。そこを修正しないと。
盛多:十三夜というのはいつになるんですか?
香月:十三日目です。
日髙:一歩手前って書いてますよね。一日前っては書いてないので……。
盛多:問題はないかなと…。あと何かありますか?
町田:この3作品の中で大賞を決めるということですよね?
盛多:それでいいかな?と……。
町田:私は『博多発新宿行き』が大賞かなと。『水たまりの夜に』もいいですが、『博多発新宿行き』をラジオドラマで聴きたいです。
この3作の中で、一番、世界観が大きいですよね。
松尾:時空も動いてますしね。
町田:はい。面白いと思います。
盛多:票数の順番からいうと、『水たまりの夜』『博多発新宿行き』『カレイの煮つけはパンに合う?』ですが……カレイの話は、香月さん、どうですか?
香月:個人的にはあまり趣味ではないかな。ちょっと泥臭いし、聴いていて清々しい気持ちにならないからね。
盛多:確かに、そういう意味でいくと、博多発の方がと思いますが……水たまりの方が情緒的に作れるかなと……うーん。
日髙:それぞれ違うから、迷いますよね。
松尾:3本とも全然ジャンルが違うから、選べないですね。
香月:やっぱり私は、十三夜という呼び名が違うから気になりますね。
盛多:一歩手前と書いているから、許容範囲じゃないでしょうか?
香月:しかし、満月の1日前は待宵月と明確に決まっているからね。
松尾:作家さんはわかって書いているんですよね?
香月:わからないね。読み手としては間違っているなと思って読みました。
盛多:十三夜とは?
香月:旧暦の13日ですね。旧暦の14が月で、旧暦の15日が満月。
盛多:15日の一歩手前だから、14か……なるほど。
香月:だから、(詳しい人が聴いたら)クレームがくるんじゃないかなと。
盛多:一応、作家の方に確認しましょう。14日だったら、何でしたっけ?
香月:待宵月です。九州支部のHPに掲載した時に「間違ってる」と言われると説明しないといけないから。ちょっと気になったので。
盛多:わかりました。確認します。他に何かあります?
松尾:どれも良いと思うんです。ジャンルが全然違うし。私は、頼りなくてクセのある水たまりくんの声が聴きたいです。キレイな月の声も聴きたいと思います。
日髙:何歳くらいの声でしょうかね? 水たまりくんは。
松尾:少年ではないですよね。20代、30代くらいかな? 月はちょっと上で、色っぽいキレイな澄んだ声で……。
香月:声を加工しても楽しいかもしれないね。
松尾:ええ。看護師の咲子さんはキャリアウーマン的で……3人ともクセのある声がいいかも。一度聞いて忘れないような声がいいなと思います。
香月:低音をカットするとか、イコライザー使ってね。
盛多:難しいな……キャスティングが……。
松尾:水たまりさんは、男の子ですよね? ボクって言ってましたから。
盛多:ええ、男ですね……えー、今までの話の流れからいくと、『カレイの煮つけはパンに合う?』は大賞ではないということでよろしいですかね。
香月さん、『水たまりの夜に』は、十三夜を確認して、訂正するとしたら、どうでしょうか?香月さんの中での評価としては変わりますか?
香月:いや、変わらないですね。ま、キレイなことはキレイだけどね。
松尾:お話として強い感じがないからですか?
香月:強いというか、振幅の幅がないかな。他のドラマは振幅の幅があるよね。確かにキレイだけどね。
町田:場所がコンビニの前から動かないからですね。
香月:それは仕方ないけどね。ただ、話がキレイで水たまりがお月さまと話をしている場面はいいけど……お天気になったらなくなっちゃうとこなんて、いいなーとは思うけどね……。ちょっとドラマとして世界が小さいかな。
町田:盛多先生、どうしましょうか?
盛多:この点数どおりにいけば、『水たまりの夜に』が大賞で、『博多発新宿行き』が優秀賞の1番で、あと『カレイの煮つけはパンに合う?』はどうでしょうか?
香月:よくある夫婦の話という気はしますね。どちらか(キャラが)変わっていたら面白いかもしれないけどね。あまりキラキラした作品ではないですよね。
町田:私は『博多発新宿行き』が聴きたいですけどね。
香月:ドラマになるんだったら、博多発が面白いと思うけどね。
町田:作るのは大変かもしれないですけど……。
盛多:雰囲気としては『水たまりの夜は』の方が作りやすいかな。
要するに、ラジオドラマとは何か? といった時に、リアリティかファンタジーを求めるのか? といったら、ファンタジーの方が聞こえはいいんですよ。
香月:そうだね。キレイだからね。
『水たまりの夜に』を(盛多さんの力で)キラキラに作ってください。
松尾・日髙・松尾「お!?(決まった?)」拍手が起こる。
香月:ただ、十三夜月の件は解決しないといけない。
盛多:それは作家に聞いて確認します。大賞に決まれば、作家の方に、ここを待宵月に変えてくださいと要求してもいいかと思います。
香月:だったら、問題ないです。
盛多:カレイの煮つけは……。
日髙:私は年齢も近いということもあって、共感する作品でした。
町田:私もです。他の皆さんからの評価も高いですし。
盛多:ですね。優秀賞の2番目という形にさせてもらいましょう。
大賞『水たまりの夜に』
優秀賞『博多発新宿行き』
優秀賞『カレイの煮つけはパンに合う?』
の3作品に決定です。
審査風景


日時:2025年 10月19日
場 所:福岡市中央区
審査委員(順不動):香月隆・盛多直隆・皆田和行・松尾恭子・日高真理子
実行委員:町田奈津子



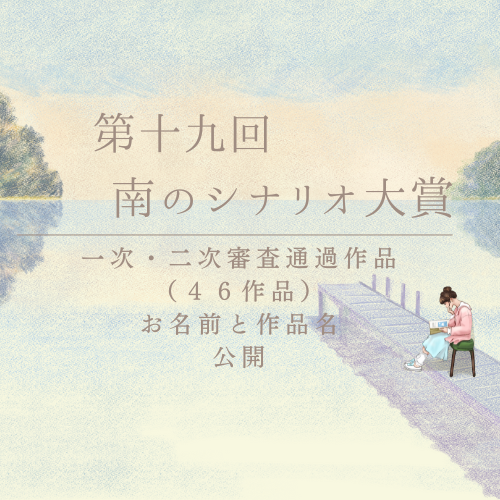

コメント